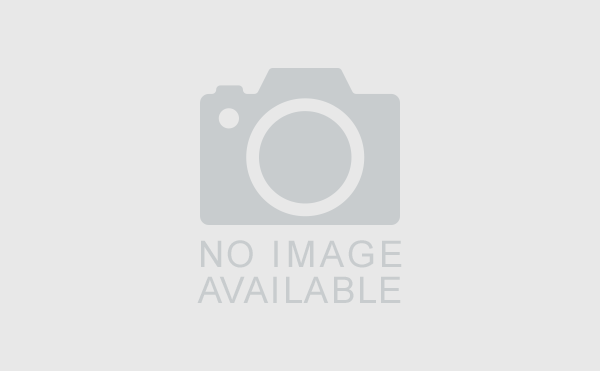安易な法人化には注意!
栃木県宇都宮市の公認会計士・税理士の岸です。
法人化の流行
最近、ネットやYoutubeなどで、節税や社会保険料の最適化のために法人化を推奨している方を多く見受けます。
確かに、現在個人事業主の方は法人化することで、所得税と法人税率の税率差や経費の対象範囲の差異を活用など、多くのメリットを受けることができます。
また、最近は法人設立も自分自身で行うことが出来たり、専門家に依頼したとしても安価で作業してくれる場合が多く、事業を法人化されている方も多いのではないでしょうか。
メリットだけではない 均等割や廃業時のコスト
しかし、法人化には当然メリットだけではなくデメリットもあります。
- 均等割の発生
例えば、法人の場合は赤字でも必ず払わなければならない均等割という税金を納める必要があります。自治体や法人の規模によって税額は異なりますが、零細小規模の法人ですと大体7~8万円程度が相場かと思います。
- 廃業時の手続き(解散、清算結了)
さらに、法人を廃業したいとなった場合には、個人のように廃業届を提出するというだけでは法人を消滅させることはできません。
法人を消滅させるためには、まず解散を行い、その後清算結了という手続きを行う必要があります。解散や清算時にはその都度確定申告が必要になり、税理士に依頼するケースが多いかと思います。
また、解散や清算結了には登記手続きが必要になります。解散や清算結了の登記は難易度が高く、ご自身で行うことは難しいかと思いますので、司法書士さんにご依頼する必要があるかと思います。
解散や清算時には上記のように確定申告の税理士報酬や司法書士への登記手続報酬などのコストが発生します。解散と清算を合わせて、最低でも30万円以上の専門家報酬は発生するものと思われます。
廃業の際には休眠という選択肢もあるが ・・・
- 均等割の節税
廃業のために解散、清算結了を行うためにはそれなりのコストが発生するため、あえて解散、清算結了を行わず、休眠というかたちで法人はそのまま残しておく方も実務上は多くいらっしゃいます。
休眠というのは、法人はそのまま残すけれども、事業は少しお休みしますよ、というものです。税務署や自治体に休眠の届出を提出します。
休眠中に実際に事業を行っておらず、事務所等の施設も存在しなければ、ほとんどの自治体では休眠中の均等割を課さない運用になっているかと思います。(ただし、自治体によって運用が異なる可能性がありますので、必ず所属自治体に問い合わせはしてください。)
- ただし、休眠期間中の登記手続きに注意
では、廃業したくなったら休眠してしまえばコストはかからないかというと、そうでもありません。
例えば、法人の登記簿には役員を登記しますが、これは一定の期間ごと(最長10年)に登記を更新する必要があります。期限までに登記が完了していない場合には、裁判所から法人代表者に過料という罰金が課せられます。金額は100万円以下です。
また、それでも解散、清算結了を行わず、登記も更新せずに放置状態となっている法人が日本には数多く存在しており、国は問題視しております。そこで、株式会社については最後の登記から12年経過している会社は国が強制的に解散登記をするというみなし解散という制度があります。
以下の法務省の統計によれば、近年は年間3万社近くの株式会社がみなし解散させられています。
休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

みなし解散させられたからといって、法人が自動的に消滅するわけではありません。前述のとおり、法人を消滅させるためには、解散の後に清算結了の手続きが必要となるためです。国は清算結了までは行ってくれません。
また、みなし解散させられても、手続きを行えば解散前の通常の法人に戻ることもできます。
しかし、手続きも司法書士等の専門家に依頼するとなればコストもかかりますし、罰金も課せられます。
素直に、所定の期限内に役員登記等を行うことが、結局は一番コストがかからない方法になると思います。
結論としましては、休眠することで均等割は節約できる可能性が高いが、役員登記等の手続きに関しては通常通り定期的に手続きを行う必要があるということです。法人を清算結了しない限り、登記手続きは永遠に続きます。
まとめ
少し脅しのような記事になってしまいましたが、私自身は法人化に多くのメリットを感じていますし、実際に多くのお客様の法人化をサポートしております。
ただし、法人を簡単に設立できるようになった現代だからこそ、廃業などの出口も検討しておく必要があると考えています。節税になるからといって法人化したけれども、法人を畳む段階でそれ以上のコストがかかったというのは避けなければなりません。
入り口から出口までの全体感を把握し、自分はそれでも法人化を行いたいか、ご検討されるとよろしいかと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【岸大路公認会計士事務所】
〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981
FAX:028-652-3907
※営業時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
mail:kishi-kaikei@lake.ocn.ne.jp
URL:https://hirocpa.com/
対応エリア:
栃木県(宇都宮、鹿沼、日光、栃木、さくら市 など)、群馬県(高崎市、前橋市、伊勢崎市、太田市 など)、茨城県、埼玉県、東京都
取り扱い業務:
税務顧問、決算申告、記帳、相続、資産税、監査、M&A