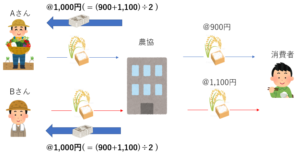相続対策としての生命保険
こんにちは!栃木県宇都宮市の公認会計士・税理士の岸です。
本日は相続対策としての生命保険についてポイントを絞ってご説明いたします。
死亡保険金の相続税務
生命保険の保険事由が発生し、相続人が死亡保険金を受け取った場合の税務については、以下の国税庁ホームページの解説が詳しいです。
国税庁タックスアンサーNo.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
そして、この死亡保険金の受取人が相続人である場合には、
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、法定相続人が3人いれば、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金の受取に関しては、相続税の計算に含めなくて良いということです。
これは生命保険の大きなメリットです。上記の例ですと、1,500万円を現預金で置いておくとその全額に相続税が課税されます。しかし、1,500万円の現預金を、1,500万円の死亡保険金が発生する生命保険契約に置き換えれば、当該死亡保険金には相続税が課税されません。
現在現預金を多く蓄えられており、生命保険に入っていないという方がいらっしゃいましたら、生命保険への加入を検討されるのもよろしいかと思われます。
生命保険の税務以外のメリット
死亡保険金は原則として遺産分割協議の対象とならない、といった特徴があります。また、原則として遺留分侵害額請求の対象にもなりません。
死亡保険金は、あくまで保険契約において定められた受取人自身が受け取るものです。したがって、被相続人の相続財産とならず、遺産分割協議を行わなくとも、受取人は死亡保険金を受け取ることができます。
例えば、相続人が多数存在する場合に、被相続人の預貯金口座を解約するためには、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本、法定相続情報の取得を行わなければなりません。そのような手続きを行っている間にも、被相続人が保有していた不動産の固定資産税の納付や、準確定申告の納税等の費用が発生してきます。
その際に、遺産分割協議を行わなくても利用できる死亡保険金というお金があれば、相続発生後の資金繰りをスムーズに行うことができます。
なお、”原則として”、遺産分割協議や遺留分侵害額請求の対象にならない、という点に注意が必要です。
裁判例の中には、保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となると解する、と示しているものがあります。
つまり、ある相続人に財産を全て渡したいため、被相続人が全財産をある相続人を受取人とした生命保険契約に全て払い込んだ場合には、他の相続人との間に著しい不公平が生じることになり、特別受益として持戻し、遺留分侵害額請求の対象になる可能性があるということです。どの程度だと著しい不公平といえるか、は弁護士等の法律専門家に確認して頂く必要がありますが、過度な生命保険の利用は危険を伴うということは覚えておいていただければと思います。
生命保険契約の注意点
・受取人の指定に注意
例えば、法定相続人ではない孫に死亡保険金を残したいと考える方がいらっしゃいます。ただし、上記の相続税の非課税枠は、法定相続人のみに適用があります。法定相続人ではない孫に対しては、非課税枠の適用はありません。
また、配偶者及び1親等の血族以外へ相続が行われる場合には、相続税額が2割加算されるルールがあります。
孫に死亡保険金を残す際には、通常よりも相続税が多く発生する可能性があるという点に注意いただければと思います。
・保険契約期間中の資金繰りに注意
一旦生命保険に加入すると、保険料相当の預貯金が保険契約に替わるため、保険事由が発生するまでは預貯金が自由に使用できないという点に注意が必要です。
途中で解約して解約返戻金がもらえるタイプの保険もあるかと思いますが、商品によっては解約返戻率が低いものもあり、結局は保険に入って損をしてしまったということにならないよう注意が必要です。
・保険商品選びは慎重に
生命保険も様々な商品があります。その中から保険の初心者が最適な保険を選ぶのは非常に難しいです。
そのような知識が不十分ではない保険契約希望者を狙って、多額の手数料の請求や粗悪な保険商品の販売を勧めるような業者も一定数存在します。対策としては、保険会社に全て任せず自分でも保険についての知識を学んだり、信頼のおける保険仲介会社の担当者に相談するのが良いかと思います。
まとめ
生命保険について相続対策という観点からポイントを絞ってご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。利用にあたっての注意点はあるものの、生命保険はうまく活用できれば相続対策として非常に有効なツールです。
自身でもよく保険について勉強し、自分にあった生命保険を選べると良いかと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【岸大路公認会計士事務所】
〒320-0065
栃木県宇都宮市駒生町1675番地8
TEL:028-652-3981
FAX:028-652-3907
※営業時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
mail:kishi-kaikei@lake.ocn.ne.jp
URL:https://hirocpa.com/
対応エリア:
栃木県(宇都宮、鹿沼、日光、栃木、さくら市 など)、群馬県(高崎市、前橋市、伊勢崎市、太田市 など)、茨城県、埼玉県、東京都
取り扱い業務:
税務顧問、決算申告、記帳、相続、資産税、監査、M&A